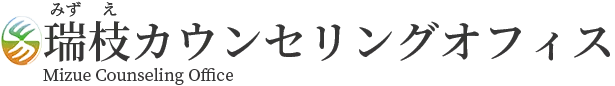Clients
Clients
クライアントの方へ
クライアントの方へ

私たちのクライアントさんは・・・
私たちのクライアントさんは・・・
-
■気分障害圏(うつ病、躁うつ病、気分変調症、適応障害)■それらのいずれか、あるいは複数が重なった不自由に苦しむ方たちが多いです。■発達障害圏(自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、境界知能、WAISディスクレパンシー、聴覚情報処理障害など)■また、そのようなクライアントさんのご家族もサポートしています。■トラウマ関連(PTSD、複雑性PTSD、解離性障害、いわゆる愛着障害)■その一方、精神科医やカウンセラーから「あなたは病気じゃない」「あなたは大丈夫」など■強迫性障害
- と言われたが、誰にも相談できない悩みを抱えている・・・というタイプの方もサポートしています。
私たちの提供する心理カウンセリングは・・・
私たちの提供する
心理カウンセリングは・・・
『統合的心理療法』です。
”技法としては、クライエントの認知・行動・感情・身体感覚(場合によっては関係性やシステムも含む)のうち、その時々で最も必要なものに、場合によってはすべてに、順番にアプローチするというものです。”(福島哲夫他『心理療法統合の手引き』, p3, 誠信書房,2024年)
実際は、どのようなカウンセリングになるのでしょうか?
カウンセラーは一人で何役もこなすことになるので、その役を、馴染みのある人物像に例えながら、カウンセリングの流れをご説明しましょう。
”技法としては、クライエントの認知・行動・感情・身体感覚(場合によっては関係性やシステムも含む)のうち、その時々で最も必要なものに、場合によってはすべてに、順番にアプローチするというものです。”(福島哲夫他『心理療法統合の手引き』, p3, 誠信書房,2024年)
実際は、どのようなカウンセリングになるのでしょうか?
カウンセラーは一人で何役もこなすことになるので、その役を、馴染みのある人物像に例えながら、カウンセリングの流れをご説明しましょう。
FLOW
FLOW
例えを使った総合的心理療法の
カウンセリングの流れ
例えを使った総合的心理療法のカウンセリングの流れ
総合的心理療法のカウンセリングの流れを例えを使ってわかりやすく説明します。
-
案内係
- 案内係の登場
- 案内係の登場
- まずはニコニコした「案内係さん」が迎えてくれます。
困りごとの内容に応じて、最適なフロアを案内してくれます。

-
学者
- 学者の登場
- 学者の登場
- そのフロアにドキドキしながら入ると、そこには「学者さん」が待っています。
緊張しながらも困りごとをどんどん話している内に、ちょこちょこ質問が入ってきて、最終的には、目下の見立てと、今後の方針や予想が伝えられます。(心理専門職は、医学的診断を下すことはできませんが、臨床心理学的見立てはしっかり行います)

-
教師
- 教師の登場
- 教師の登場
- 次は、「学校の先生(教師)」にバトンタッチ。
これから必要な知識が、心理教育(psycho-education)として伝授されます。
もちろん、セロトニンがどうのこうのなどの、退屈な講義ではありません。
例えば「うつの状態って、自転車のチェーンが外れた状態に例えるとわかりやすいですね」など、今後、一緒に取り組んでいく上での共通言語になるわけです。

-
トレーナー
- トレーナーの登場
- トレーナーの登場
- 準備が整ったらいよいよ、「トレーナー」の登場です。
スポーツと全く同じ。トレーナーに、あるべきフォームを教えてもらって、後は自分で練習する。
その成果を次回、トレーナーに見てもらって、うまくいった点、まだ足りない点をそれぞれ確認する、その繰り返し。シンプル!
ここで込み入ってくるのは、困りごとに応じて、「何の」フォームを「どう」修正すべきかが、違ってくる。
考え方なのか?感じ方なのか?実際の行動なのか?それとも自分の価値観なのか?
だから「○○療法」「○○セラピー」などが、おびただしく存在するのです。
私たちは、その主要なものを身につけた上で、でも「○○療法」などを最初の1ページ目からやっていると、とても時間と労力がかかる、(その余裕のあるクライアントさんは決して多くはない)・・・だからクライアントの皆さんに今、最も必要な、その「何の」と「どう」を、ピンポイントで具体的にお伝えするようにしています。集中!集中!
その結果「これから○○療法をやります」という宣言はなくとも、カウンセラーとやり取りを続ける中で、自然に実質的に、取り組んでいることになるわけです。
(実は、これが認知行動療法のエッセンスなんですよ、マインドフルネス瞑想のエッセンスなんですよと・・・、後からお伝えする場合も多いです。)
.webp)
-
母親
- 母親の登場
- 母親の登場
- トレーニングを続ける中で、ある日、何の予兆もなく、すっかり忘れていたある日の出来事がものすごくリアルに思い出されて、涙が止まらなくなったとしましょう。
すると、トレーナーは「お母さん」(以下、母親役)とバトンタッチです。
「そんなことがあったんだね・・・そりゃあ、しんどいね・・・」としんみり聞いてくれます。
無理のない語れる範囲で、クライアントさんも、ポツポツと言葉にしていきます。
「それって、○○だったんじゃない?」と母親役がさりげなく水を向けると「そう・・・、そうだ・・・、その通りでした・・・」とクライアントさん。
「(この人は、ほんとに私のことがわかってるんだ・・・伝わってるんだ・・・)・・・」とまた涙がこぼれます。
この母親役は、トレーナーに負けないくらい、出演頻度は高いです。
困りごとによっては、「案内係」が最初にこのフロアを案内してくれる場合も多いです。
また、さりげなく、「これが悲しみ、という感情なんですよ」と一瞬、トレーナーが顔を出しては引っ込む、という場面もまま、あります。

-
トレーナー
案内係-
→同じテーマが続けば、
トレーナーの登場→カウンセリングで、
今までにないテーマが
浮上したなら、案内係 -
→同じテーマが続けば、トレーナーの登場→カウンセリングで、
今までにないテーマが浮上したなら、案内係 - さて、この説明で、『統合的心理療法』の実際のイメージが伝わったかと思います。
しばらく同じテーマが続いているなら、毎回、最初から「トレーナー」が登場します。
ある日のカウンセリングで、今までにないテーマが浮上してきたなら、「案内係」がその時点で再登場する、という段取りです。
もちろん、「案内係」「学者さん」「学校の先生」「トレーナー」以外にもカウンセラーがこなす役柄があります。
興味のある方は、続きをこちらから。
.webp)

-
-
父親
- 父親の登場
- 父親の登場
- 「お父さん」(以下、父親役)も、時に呼び出されます。
クライアントさんは、頭ではわかっているが、どうしても流されてしまう、そんな自分が出てくるとき、なすすべがない方、多いです。
相手が物であろうが人であろうが、境界線が作れない、つまり依存や嗜癖の病理です。
そんな時、流されてしまうその全貌を知り尽くした上で、(つまり、クライアントさんの事情を知り尽くして弁護する母親役の言い分もすべて飲み込んだ上で)なお、ダメなものはダメと、毅然と指摘してくれる父親役が、必要なのです。
それは「あー、叱られた・・・」とシュンとなっては、また、繰り返すためではなく、その父親役がもっている力、境界線を作る力、それを自分の中に取り入れるきっかけにするためですね。
父親役に言われなくても、自分の中に、父親役がいる、そんな自分に成長するために。

-
老賢者
- 老賢者の登場
- 老賢者の登場
- カウンセラーは必要とあれば、「老賢者」の役回りもします。
人生の知恵を伝える、あごひげの伸びた仙人のイメージでしょうか。
例えば、せっかくトレーニングがいいところまで来たのに、人生の思わぬ荒波で、振り出しにもどったような気分になった時。
「人は、ピンチの時、とれる作戦は4つしかないんじゃよ。」
「何だか、わかるかね?」
「逃げる、戦う、耐える、そして助けを求める、じゃ」
「つまり、逃げるも、立派な作戦なんじゃな・・・」

-
巫女
- 巫女の登場
- 巫女の登場
- 不審に思われるかもしれませんが、「巫女(みこ)さん」(以下、巫女)という役割もあります。
巫女は、口寄せの能力をもつ霊媒師の一型です。
(口寄せとは、霊的存在を自分に憑依させて、その言葉を語ること。)
こんなテーマが、カウンセリングに関係あるのでしょうか?
「霊的存在」を「クライアントが自覚していないクライアント自身の要素」と言い替えれば、事情が見えてきます。
一番イメージしやすいのは、クライアントの夢の扱いでしょう。
その方法論には、フロイト以来、100年の歴史がありますが、以下に述べるものはユングのそれに近いです。
まず、クライアントと深く関わっているカウンセラーの生身の存在に、クライアントの自覚が及ばない要素としての夢を「憑依」させます。
(具体的には「深く内的に味わう」ということです。)
そしてその結果が「口寄せ」として、クライアントにフィードバックされる。
それがクライアントに、自分自身をより深く知るための気づきを与えてくれる訳です。
カウンセラーに「憑依」する、「クライアントが自覚していないクライアント自身の要素」としては、夢よりもストレートなものとして、クライアントがカウンセラーに無自覚に抱く、様々な感情を挙げることができます。
それをカウンセラーが、適切なタイミングで口寄せとして、治療的にクライアントに返すことができたなら、クライアントは、自身の対人関係の不自由について、突破口を見出すことができるでしょう。
(これは転移の解釈と呼ばれます。クライアントの相手がカウンセラーでなければ、クライアントの無自覚な感情に、その相手も無自覚に振り回され、お互いの関係が泥沼にはまっていくからです。)

-
弁護人
- 弁護人の登場
- 弁護人の登場
- もう一つ、大切な役柄として「弁護人」があります。
クライアントさんは、社会生活を送る中で、孤立無援の方、多いです。家族の中で、地域で、学校で、職場で、誰も、自分のことをわかってくれない・・・。
その時、カウンセラーが、クライアントの不自由と苦しみと求める配慮について、関わる人たちに、わかりやすく代弁する。

-
土地の人
- 土地の人の登場
- 土地の人の登場
- 「土地の人」という役割もあります。
その土地の人は、野菜ならあそこの八百屋が安くて新鮮、など、その土地に馴染みがあるからこその情報と人脈を持っています。
私たちは、メンタルヘルスに関連する土地の人です。
リハビリのためにどんな施設があるのか?
メンタルヘルスに理解のある弁護士事務所、不動産屋ならどこか?

-
政治家
- 政治家の登場
- 政治家の登場
- 意外かもしれませんが、「政治家」という役割もあります。
典型的な場面は、クライアントさんとそのご家族が対立し合っている場合。
どちらが正しいかと裁くのではなく、お互いの利害をいかに調整して、双方が納得のいく落とし所を見つけるか。
その粘り強い交渉力を発揮するのも、カウンセラーの真骨頂です。
もっと言えば、一人のクライアントさんの中にも複数の「自分」がいて対立している場合、その調整も「政治家」の役割ですね。

-
証人
- 証人の登場
- 証人の登場
- そして最後は「証人」(witness:目撃者、生き証人)としての役割。
自分なりに、できるだけのことはやった、でも今の生活状況をこれ以上、変えることは現実的にはできない・・・。
どしようもない八方塞がりの状況は、残念ながら存在します。
そのような時でも、それでも、カウンセリングに訪れる、そのクライアントの生き様を、生存している事実を、誠実な証人としてこころに刻みおく、その役割もあります。