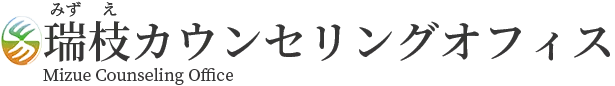F&Q
F&Q
よくある質問
よくある質問

-
- カウンセリングはどのような流れで進みますか?
- 心理療法によっては、合計の実施回数や、実施間隔、使用するワークシートなどがあらかじめ構造化されたものもあります。当オフィスでは、一回のカウンセリングがその時間内である程度完結し、クライアントと、取り組むテーマ、実施するペース、全体的な見通しなどをその都度共有しながら、一回一回を積み重ねて行くスタイルを取っています。一回のカウンセリングの中での大まかな流れは、「例えを使った総合的心理療法の流れ」を参照ください。
-
- どのような資格や経験を持ったカウンセラーがいますか?
- 当オフィスでは、臨床心理士/公認心理師/精神科専門医、そのいずれかの専門資格を持ったカウンセラーが在籍しています。加えて採用の条件として、精神医療の現場での3年以上の臨床経験を要求し、精神科ユーザーの困りごとに対応できるスキルを担保するようにしています。
-
- どんな問題でもカウンセリングを受けられますか?
- 原則として、クライアント自身が困っている問題であれば、これをカウンセリングで相談してはならない、という制約はありません。「相談する」ということと「解決する」ということを分けて捉えるとよいでしょう。カウンセラーが「解決できない」ことはたくさんありますが、クライアントが悩んでいることを「一緒に考える」ことはできます。一人で悩んでいることと、誰かが一緒に考えてくれること、その違いの大きさは体験されると分かります。カウンセラー自身が解決方法を提案できない場合、それが可能な専門職を紹介することもできます。「こんなことを相談するのは筋違いかもしれないな・・・」と悩んだ場合は、相談されることをおすすめします。
-
- カウンセリングでプライバシーは守られますか?
- ご安心ください。たとえご家族であっても、クライアントの同意がなければ、カウンセリングの内容をカウンセラーが口外することはありません。ただし、クライアント自身に生命の危険が迫っている場合など、特定の場合に限り必要最小限、関係者に情報を伝える場合はあります。詳細は、プライバシーポリシー(特に第7条)をご確認ください。
-
- カウンセラーに相談することと、家族や友人に相談することと、何が違いますか?
- カウンセラーは、数多くある対人援助職の一つですが、その「対人援助」の本質を知ると、その違いが見えてきます。当オフィスの教育コンテンツでは、対人援助の5つの要件として、以下を挙げています。家族・友人との異同を整理してみましょう。
①:援助の対象が、個別性への配慮を要する「人」である。・ここは両者ともに似ています。あなたをかけがえのない固有の人として向き合っています。
②:カウンセラー/クライアントとの間に、一定の契約関係がある。③:カウンセラー/クライアントが、自らの意志でその契約を解除できる。・ここが大きく違います。親族・友人は「契約関係」には馴染みません。そのよい面/悪い面があります。・カウンセラーなら、契約以外のこと、例えば深夜でも話を聞いてくれる、などは望めませんが、家族・友人なら話を聞いてくれる可能性があります。・その一方、カウンセラーなら気に入らなければ会わないことができますが、家族・友人ならそれが難しくなる。
④:援助の内容が専門性を有し、被援助者に与える影響が比較的大きい。・この専門性の有無も、両者で大きく違う点です。専門性のない家族・友人ではとても思いつかない助言をしてもらえる可能性があります。
⑤:援助者と被援助者との間の良好な信頼関係が、援助の有効性の基礎である。・ここも両者ともに似ています。ただし、カウンセラー/クライアントの信頼関係は「契約関係」に基づく、比較的安定はしているが一定の距離感がある。家族・友人なら、お互いの体調・気分に左右されて比較的不安定でとても接近したかと思うと急に突き放されるリスクがある。また、プライバシーが守られない懸念も残る。
このように整理すると、カウンセラー/クライアントの契約関係を維持できる程度の、身体的/精神的/経済的な余裕がある方が、家族・友人には相談できない内容をカウンセラーに相談する、という状況は、大いにあり得るわけです。
-
- カウンセリングにはどのくらいの費用と時間がかかりますか?
- 当オフィスでは、カウンセリング料金はカウンセラーごとに設定されています。料金はこちら。
カウンセリングにどれぐらいの時間がかかるか(終結までにどの程度の期間を要するか)は、かなりケースバイケースになります。典型的ないくつかのパターンを以下にまとめてみます。
A:1回の面接で終了する。・相談内容がかなり具体的で、そこで提案された自助努力の方法をクライアント自身が取り組める場合。
B:Aを不定期に繰り返す。・2〜3ヶ月に1回、半年〜1年に1回、数年に1回など、まちまちです。
C:一定期間、特定のテーマについて取り組む。※以下は例。・休職中、復職までの期間(例えば半年間)に、アンガーマネジメントに取り組む。・高校合格までの間、勉強への集中力と生活リズムの維持に取り組む。・フラッシュバックが消退するまで、EMDRに取り組む。(例えば、全5回等。)
D:心身のメンテナンスを目的に定期的に利用する。・面接の間隔は、1〜2週毎、4〜8週毎など、まちまちです。・一定の小康状態にまで達した後の、その維持の役割。・ここに、必要に応じてCが挿入される場合も多い。
E:精神障害の療養のサポートを目的に定期的に利用する。・面接の間隔はDと同様。・複雑性PTSDを背景にもつうつ病、自閉症スペクトラム障害の生き辛さ、強迫性障害など、その不自由の緩和に比較的長期間(年単位)を要し、保険外来だけではサポートが不十分なケース。