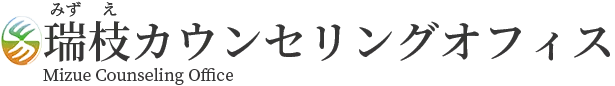Educational content
educational content
教育コンテンツ
教育コンテンツ

うつ病の治し方で
最初に知るべき3項目
最初に知るべき3項目
うつ病の治し方で最初に知るべき3項目
うつ病の治し方で最初に知るべき3項目 その1
うつ病にかかったご本人も、そのご家族さんも、うつ病の療養生活をはじめる際にこれだけは、なんとしても知っておいて頂きたい、そのような内容をまとめています。その1回目です。うつ病とは「チェーンが外れた自転車の状態である」というイメージが有用だ、という説明から入ります。自転車が動かない原因は、運転者のやる気や性格ではなく、はたまた、タイヤがパンクしているわけでもない。このイメージが、うつ病の原因を、その本人(運転者)や、身体(タイヤ)に求めてしまう過ちから、救ってくれます。またこのシリーズで扱う知識は、うつ病だけでなく、適応障害・気分変調症・躁うつ病など、他の精神疾患に現れる抑うつ状態全般に共通です。
うつ病の治し方で最初に知るべき3項目 その2
1回目の知識を踏まえて、いかに外れたチェーンをかけ直すか、という療養の初期のテーマを扱っています。キーワードは自己治癒力です。まず、身体の外傷がどのように治っていくのか、その一般的な過程を紹介して、自己治癒力の具体的なイメージを共有します。その上で、うつ病の場合はどうなのか。外れたチェーンが自己治癒力で、ムクムクと歯車に自らかかっていく。療養のポイントは、その自己治癒力を促進するものを生活の中でたくさん用意し、阻害するものを出来るだけ排除する。それが療養の本質になります。その具体的な項目を一覧表にまとめています。
うつ病の治し方で最初に知るべき3項目 その3
3回目は、2回目で説明したチェーンをかけ直すテーマに続き、そのせっかくかかったチェーンがまた外れないように、どうやってペダルを踏み込んでいくかという、うつ病の療養の次のステップ、つまり、リハビリについて扱っています。ペダルを踏み込むとは、具体的には、日常生活の全てがそこに含まれてきます。世には「うつ病には運動がよい」などの情報があふれていますが、無理に散歩をして、チェーンがまた外れてしまった、というケースが極めて多いです。まずは自宅内でできることが増えていく必要があります。寝ている時間が多い方は、まずは座っている時間が増えることが必要です。その努力が、その方にとっての「適切なペダルの踏み込み方」になります。その方が例え短時間であっても散歩をするなら、あっという間に、またペダルが外れてしまうでしょう。まずは自宅内でどんな活動があるのか、その先の自宅外ではどんな活動が適切なのか、ものすごく具体的に説明していきます。
感情リテラシー入門
感情リテラシー入門
感情リテラシー入門 第1回 感情とは
療養生活の中で、感情にまつわる困り事はとても多いです。感情に振り回される一方で、感情がわからなくて困る、という場合もあります。感情とどのように付き合っていけばよいのでしょうか。「感情リテラシー入門」はその指針を明快にお伝えするシリーズです。「リテラシー」とは、特定の情報に関する「読み書きのスキル」を意味します。つまり「感情リテラシー」とは、感情という情報に関する読み書きのスキル、を意味します。第1回目は、そもそも感情をどのように捉えたらよいか、その整理から始まります。そして、感情を、状況→感情→行動、というセットで捉える見方をお伝えします。
感情リテラシー入門 第2回 感情リテラシーのメリット
療養生活の中で、感情にまつわる困り事はとても多いです。感情に振り回される一方で、感情がわからなくて困る、という場合もあります。感情とどのように付き合っていけばよいのでしょうか。「感情リテラシー入門」はその指針を明快にお伝えするシリーズです。「リテラシー」とは、特定の情報に関する「読み書きのスキル」を意味します。つまり「感情リテラシー」とは、感情という情報に関する読み書きのスキル、を意味します。第2回目は、感情を、状況→感情→行動、というセットで捉えることのメリットについて整理します。一つは、そもそも感情は、特にネガティブなものであっても「抱いてもよいのだ」というリフレーミングがしやすいということです。そして、具体的にどんな行動をとることが正解なのか、という枠組が得られる点です。
感情リテラシー入門 第3回 感情の分類その1 幸せ・さみしさ
「感情リテラシー」とは「感情という情報に関する読み書きのスキル」を意味します。その第3回目は、いよいよ具体的な感情の分類に入ります。その1回目の今回は、「愛と悲しみ系」という大分類の中の、しあわせ、さみしさ、という感情について、状況→感情→行動のセットで整理していきます。特に、感情が分からない方、感情を押さえ込む方、感情に振り回される方、それぞれの典型的なケースもご紹介します。
感情リテラシー入門 第4回 感情の分類その2 悲しみ・憎しみ・罪悪感
「感情リテラシー」とは「感情という情報に関する読み書きのスキル」を意味します。その第4回目は、感情の分類を扱う2回目です。今回は、「愛と悲しみ系」という大分類の中の、悲しみ、憎しみ、罪悪感という感情について、状況→感情→行動のセットで整理していきます。特に、前回で扱った「さみしさ」と、今回の「悲しみ」の区別を学びます。
感情リテラシー入門 第5回 感情の分類その3 イヤイヤ系
「感情リテラシー」とは「感情という情報に関する読み書きのスキル」を意味します。その第5回目は、感情の分類を扱う3回目です。今回は「イヤイヤとワクワク系」のイヤイヤ系(嫌悪・憂うつ・恐怖・不安)について、その知識を活かすための、前提となる注意点についてまとめています。それらの感情は、促される行動が「回避(逃げる)」になります。しかし「逃げるのはよくない」という価値観をお持ちだと、感情リテラシーがうまく活用できません。「人がピンチの時にとれる行動は4つしかない」という説明から入ります。
感情リテラシー入門 第6回 感情の分類その4 嫌悪・憂うつ
「感情リテラシー」とは「感情という情報に関する読み書きのスキル」を意味します。その第6回目は、感情の分類を扱う4回目です。今回は「イヤイヤ系」の中の「嫌悪」「憂うつ」についてお伝えします。「嫌悪」は、生存にとって有害な環境によって発信され、その環境から身を離すという行動を促進します。「憂うつ」は、その嫌悪の予感によって発信されます。でも、その環境から身を離せない場合はどうしたらいいでしょうか?受けたダメージを「デトックス」する方法についてもお伝えします。
感情リテラシー入門 第7回 感情の分類その5 恐怖
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第7回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその5回目。いよいよ、感情リテラシーの中でも最重要の一つ、恐怖について取り組みます。ポイントは2つ。一つは、恐怖が発信される状況がとても多彩であること。もう一つは、恐怖という感情があまりに不快なため、それを「カムフラージュ」するこころのメカニズムがこれもまた多彩にあるという点です。
感情リテラシー入門 第8回 感情の分類その6 不安
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第8回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその6回目で、不安について取り組みます。不安という感情は、「恐怖が予感される状況」で発信されます。よって、不安の感情リテラシーの上達には、「自分は何を恐怖しているのか」の自覚がとても大切になります。そして、不安に対する適切な行動は「生存競争に必要な警戒の強化」、キャッチフレーズ的にまとめると「対策とったら耐えるだけ」と整理しています。その「耐える」方法が実は、マインドフルネスのための各種スキルが役に立つこともお伝えします。
感情リテラシー入門 第9回 感情の分類その7 怒り
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第9回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその7回目で「怒り」について取り組みます。怒りという感情は「自分の行動・思考のペースが乱され続ける状況」で発信されます。促される行動は「攻撃(実力行使)のアピール」となります。怒りの感情リテラシーは、メンタルヘルス上とても重要です。「行動・思考のペースが乱され続けている状況」は心身ともにダメージが大きいため、速やかな対処が望ましいからです。怒りの感情リテラシーが苦手な方には、二つのタイプがあります。一つは、怒りに振り回されるタイプ。もう一つは、怒りを必要以上に抑制してしまうタイプ。それぞれの心理的背景や対策について整理していきます。
感情リテラシー入門 第10回 感情の分類 その8 イライラ
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第10回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその8回目で「イライラ」について取り組みます。イライラという感情は「怒りが予想される状況」で発信されます。促される行動は「攻撃(実力行使)のアピールの準備、あるいは自制する」となります。具体例として、ATMの前の方がもたもたしている場面を挙げて、イライラへの対処には大きく二つの方向性があることをお伝えします。そして「怒りが予想される状況」で発信されるイライラの感情リテラシーの向上には、怒りについて感情リテラシーがポイントとなることもお伝えします。誰、あるいは何に、自分の何のペースが乱されているのか、それを自覚すること。それを踏まえて、相手や状況を変えるための行動をとるのか、自分の行動・思考を変えるのか、その二つの方向性にそって対処を整理していきます。
感情リテラシー入門 第11回 感情の分類 その9 自信
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第11回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその9回目で「自信」について取り組みます。自信という感情は「自分の生存能力を高く評価できる状況」で発信されます。促される行動は「生存競争に必要な警戒を解く」となります。具体的には、準備もサポートも不要なまま生存競争の場に飛び込める状態です。そこでうまく生存できたなら一層、自信がつくという好循環となりますが、いつもそうとは限りません。すると再び「警戒する」状態、つまり「不安」という感情が発信される状況となります。ここで取るべき対策は、実は、不安の感情リテラシーですでにお伝えしています。このように、ブロックごとに見通しよく整理できる点が感情リテラシーのメリットです。そして「自信」という感情はアップダウンしてよい、という認識の重要性をお伝えします。最後に自己効力感との関連と、応用編でお伝えする内容の予告で終わっています。
感情リテラシー入門 第12回 感情の分類 その10 無力感
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第12回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその10回目で「無力感」について取り組みます。無力感という感情は「自分の生存能力を低くしか評価でない状況」で発信されます。促される行動は「生存競争の弱者であることのアピール」となります。具体的には、「さみしさ」「悲しさ」「不安」などの感情が混在している場合が多いので、それぞれの感情リテラシーに沿って対処することになります。その結果「自信」が回復し「無力感」が軽減していくことが期待できます。その一方、「無力感」が長く続いてしまうケースも多いです。その原因を二つに整理していきます。一つは、①:他者へサポートを求めることができない。具体的には、・自分のポリシーではない、・裏切られた続けた過去がある、・周囲に誰もいない。もう一つは、②:生存競争の場を、生存できそうな場に移すことができない。具体的には、・自分のポリシーではない、・周囲からの圧力、・経済的な問題、が挙げられます。
感情リテラシー入門 第13回 感情の分類 その11 希望
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第13回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその11回目で「希望」について取り組みます。希望という感情は「自分の未来の可能性を信じることができる状況」で発信されます。促される行動は「生存戦略のためのあらゆる行動の加速」となります。しかし、希望という感情が抱けない場合はどうしたらよいでしょうか?そこで今回は、人間の持つ「信じる」という機能について、南アフリカ共和国の元大統領、ネルソン・マンデラを例にお伝えします。そして「信じる」機能の活性化のポイントを5つ、挙げています。1:自分の短所も活用できる能力、2:感情コントロール能力、3:孤立するリスクを引き受ける能力、4:人生のピンチを成長の機会に変えられる能力、5:自分の立場を強めに見積もることができる能力、この5つです。
感情リテラシー入門 第14回 感情の分類 その12 喜びと失望
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第14回目です。感情の分類を整理するテーマが続いていますが、今回はその12回目で「喜び」「失望」について取り組みます。まず、喜びという感情は「希望の達成した状況」で発信されます。促される行動は「自分の生存能力の高さのアピール」となります。ポイントは2つ。一つは、希望が抱けないと喜びの感情も抱けない、という点。もう一つは、最初のハードルは低くして、「小さな希望」を抱いて「小さな成功体験」を得て「小さな喜び」を実感する、そのリハビリが重要という点です。次は「失望」。この感情は「希望が失われる」という状況で発信され、促される行動は「生存競争の弱者であることのアピール」となります。「失望」には、「さみしさ」「悲しさ」「無力感」などの他の感情が混在している場合が多く、それぞれの感情リテラシーに沿った対策を提案しています。
感情リテラシー入門 第15回 不安の感情リテラシー:応用編 その1
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第15回目です。感情の分類を終えて、応用編に入ります。まずは、不安の感情リテラシーをどのように活用すればよいか、それがよくわかるケース(実際の患者さんの例を複数取り混ぜた架空のケース)を二つ紹介します。一つは、30代の主婦、ご主人の出張中に不安で眠れないケース。もう一つは、50代男性の会社員、舌の痛みと違和感で気分が落ち込むというケースです。いずれも、不安の背景にある恐怖に向き合うことの重要性をお伝えしています。
感情リテラシー入門 第16回 不安の感情リテラシー:応用編 その2
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第16回目です。感情の分類を終えて、応用編に入っています。不安の感情リテラシーをどのように活用すればよいか、それがよくわかるケース(実際の患者さんの例を複数取り混ぜた架空のケース)を紹介した、前回(その1)に続いて、その2、になります。ケースの一つは、40代女性でパート勤務、高齢の両親の体調が悪化する都度、不安で仕事が手につかなくなるケース。「対策とったら耐えるだけ」という不安の感情リテラシーが如何に有効だったかをお伝えします。もう一つは、20代の女子大学生で「急にわけもなく胸がざわざわする何とも言えない不安がおそってくる」ケース。実存的不安と呼ばれる不安への対策をまとめています。
感情リテラシー入門 第17回 怒りの感情リテラシー:応用編 その1
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第17回目です。感情の分類を終えて、応用編に入っています。怒りの感情リテラシーをどのように活用すればよいか、特に、怒りに振り回されてしまうタイプの方を念頭に整理しています。まず、怒りに関するログ(記録)を取ることで、怒りのさなかでも「自分は怒っている」と自覚できるようになる(メタ認知が得られる)ことの重要性をお伝えします。その後に、ケース(実際の患者さんの例を複数取り混ぜた架空のケース)を二つ紹介します。一つは、こだわりの強い主婦のケース。認知をゆるめることで怒りをコントロールします。もう一つは、母から虐待を受けてきた女性のケース。攻撃の相手をすり替えているこのとの自覚を通じて怒りをコントロールします。
感情リテラシー入門 第18回 怒りの感情リテラシー:応用編 その2
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第18回目です。感情の分類を終えて、応用編に入っています。怒りの感情リテラシーをどのように活用すればよいか、特に、怒りを抑えてしまうタイプの方を念頭に整理しています。40代女性、専業主婦で夫に不倫の疑いがあり以後、頭痛に苦しんでいるケース(実際の患者さんの例を複数取り混ぜた架空のケース)を紹介します。学びのポイントは、・「怒り」という感情を抱いてはいけないという認知の修正、・「怒り」という感情の実感、・それによる頭痛の軽減、・怒りの感情リテラシーにそった適切なアピールの方法、・そのための恐怖の感情リテラシーへの取り組み、が挙げられます。
感情リテラシー入門 第19回 自信の感情リテラシー:応用編 その1
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第19回目です。感情の分類を終えて、応用編に入っています。自信の感情リテラシーをどのように活用すればよいか、2回に分けてお伝えする、その1回目です。まず、復習から始めます。自信という感情は、自分の生存能力を高く評価できる状況で発信され、生存競争に必要な警戒を解くという行動を促します。でも、自分の生存能力を高く評価する基準とは、具体的に何でしょうか?診察では、その基準には「自分軸」と「他人軸」という二種類があると説明しています。「他人軸」とは、数値や○✖️など、他者と共有しやすい評価基準です。「自分軸」とは、1日1日の小さな変化など、他者と共有しにくい評価基準です。この二種類の評価基準を上手く使い分けることが、自信の感情リテラシーに重要であるとお伝えしています。また、「自信」と似た言葉に「自己効力感」という用語があります。自己効力感とは、自分がどれだけ自分の現実に変化を与えることができるか、その手応えのことですが、自信との関連についても触れています。
感情リテラシー入門 第20回 自信の感情リテラシー:応用編 その2
「感情という情報に関する読み書きのスキル」を身につける感情リテラシーのシリーズ、今回はその第20回目で最終回です。自信の感情リテラシーをどのように活用すればよいか、2回に分けてお伝えする、その2回目です。うつ病で休職中の40才男性の、実際の患者さんを取り混ぜた架空の例を題材に、自分軸と他人軸の使い分けのコツをお伝えします。自分軸を見つけてそれに取り組む結果、他人軸での自己評価が上がり、それが、自己効力感を上げ、自信という感情を実感できる、その過程を具体的に追っていきます。
効く!マインドフルネスの基礎
効く!マインドフルネスの基礎
効く!マインドフルネスの基礎 その1 注意のコントロール
マインドフルネスという用語が指し示す精神状態は、精神疾患の種類を問わず、療養生活の中でとても大切な位置づけを持っています。なぜなら、症状にともなうあらゆる苦痛を大きく軽減させる力を持っているからです。でも「レーズンエクササイズや呼吸法、瞑想法などに取り組み、今、現在に注目しようと言われても、ピンとこなかった」という声を多く聞きます。このシリーズでは、「現在に注目する」とは具体的にどのようなことなのか、全く新しい観点から整理します。その上で、「選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みます。今回はその第1回目:「注意のコントロール」。
効く!マインドフルネスの基礎 その2 6つのチャンネルという考え方
「選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第2回目:「6つのチャンネルという考え方」。「6つのチャンネル」とは、アーノルド・ミンデルが生み出したプロセス指向心理学という心理学の一派が頻用する、人が何かを体験する際に、その情報が流れる通路、という意味合いです。その6つとは、視覚、聴覚、身体感覚、身体運動、他者との関係、世界との関係。これを一つ一つ、丁寧に見ていきます。ところでこの見方が、療養の何に役に立つのでしょうか?例えば、怒りのコントロール。怒りという情報は、身体感覚のチャンネルを介します。その際、別のチャンネル、例えば、コーヒーを淹れて飲むという、身体運動のチャンネルに、選択的注意を向けることができたなら、怒りをコントロールする余地がでてきます。また、6つのチャンネルという考え方に親しむための、簡単なワークも提案します。
効く!マインドフルネスの基礎 その3 呼吸法 前編
「選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第3回目:「呼吸法 前編」。導入として、そもそもなぜ、呼吸法なのか?という大切なポイントについて整理します。それに引き続き、呼吸法の段取りの中で、最初の「腹式呼吸」と次の「調息」について説明します。特に、第2回目で導入した「6つのチャンネル」という考え方を、復習しつつ、フル活用します。「腹式呼吸」では、自分の体に置いた手の「身体運動」に選択的注意を向ける。「調息」では、鼻の粘膜を空気が通過する「身体感覚」に選択的注意を向けます。その実際を丁寧にお伝えします。
効く!マインドフルネスの基礎 その4 呼吸法 後編
「選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第4回目:「呼吸法 後編」。息を吸って、溜めて、吐く、それを、3秒で吸って、2秒で溜めて、10秒で吐く、それを意識の中で、しっかり数える段階に進みます。数えるとは、言語なので、聴覚のチャンネルです。前編の「腹式呼吸」と「調息」は、それぞれ身体運動と身体感覚のチャンネルでしたが、それを聴覚のチャンネルに切り替える練習にもなります。それに慣れた後に広がる世界についても触れていきます。呼吸している自分が、まるで風船が膨らんではしぼんでいくような、イメージの世界。そして、吸って溜めた時の、吐きたくなる衝動。吐ききった後の、吸いたくなる衝動。最後に、呼吸法の「型」の意義についても触れています。
効く!マインドフルネスの基礎 その5 マインドフルになるために使えるアイテム
「選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第5回目:「マインドフルになるために使えるアイテム」。シンギングボウル、音楽、お香、アロマキャンドル、アロママッサージ、ムドラー、めぐリズム、足浴、ぬいぐるみ、ゲーム、頓用、パターン思考について解説します。
効く!マインドフルネスの基礎 その6 療養生活の現場から 第1部
選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第6回目:「療養生活の現場から」の第1部になります。実際に診療したケースをもとに個人情報に配慮して架空の症例としたものをご紹介します。30代男性の動悸のケース、20代女性の不安発作のケース、40代男性のマイナス思考のケースが、何に注目することで症状が和らぐのかを解説しています。
効く!マインドフルネスの基礎 その6 療養生活の現場から 第2部
選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第6回目:「療養生活の現場から」の第2部になります。実際に診療したケースをもとに個人情報に配慮して架空の症例としたものをご紹介します。40代の主婦の方のマイナス思考のケース、30代女性のイライラのケースなどをご紹介していきます。
効く!マインドフルネスの基礎 その6 療養生活の現場から 第3部
選択的注意の自己コントロール」をキーワードとして、「使えない」マインドフルネスを、明日の療養生活に活かせる「効く」スキルとして、取り出すことを試みたシリーズ、今回はその第6回目:「療養生活の現場から」の第3部になります。実際に診療したケースをもとに個人情報に配慮した架空の症例をご紹介します。明日の会社の事を考えて寝付けない30代の女性、今日も眠れるだろうかと考えて寝付けない60代の男性、慢性疼痛で寝付けない50代女性の症例が登場します。
認知リテラシー入門
認知リテラシー入門
認知リテラシー入門 第1回 「考える」機能の本質とは
ものごとを極端な白と黒で考える「白黒思考」などは、典型的な「歪んだ認知」と言われます。認知行動療法の対象となりますが、その認知行動療法がうまくいかないケースも多いです。そこで、ヒトの「考える」機能(思考)の本質にさかのぼって、それを「スキル化する」ことを狙ったものが、認知リテラシーです。今回はその初回。出発点になる、認知リテラシーの「基本セット」から紹介します。「考える」とは、「ゴールの設定」→「情報収集」→「判断」→「結論」、この4つの基本セットから成る。そしてポイントが3つ。1つ目は「思考には始まりと終わりがある」。2つ目は「思考の結論は行動に結びつき、現実に変化を与える」。3つ目は「ゴールの設定がとても重要」。いわゆる「ぐるぐる思考」がいかにこの3つのポイントを外しているかを、見ていきます。
認知リテラシー入門 第2回 「基本セット」の実例
第1回でお伝えした、認知リテラシーの「基本セット」とは、「ゴールの設定」→「情報収集」→「判断」→「結論」でした。今回の第2回では、その基本セットの実際を、スーパーに買い物に行く主婦の、架空の例を題材にお伝えします。「考える」機能をうまく使うスキルとは、具体的にどんなことなのか?「ゴールの設定」とは、例えば、これから30分で、夕食の食材を購入する、ただしメニューには残り物のキャベツの1/4玉を使う、など。「情報収集」とは、実際にスーパーに足を運び、商品棚を巡って食材を探すこと。食材を見ながらメニューに使えるか「判断」しつつ、そのメニューに必要な他の食材があるかを「情報収集」しつつと、ここは行ったり来たりになる。そして「今夜の夕食に必要な食材はこれだ」と「結論」が出て、レジに並ぶという行動で終わる。この架空の例を通じて、認知リテラシーのポイントである「思考には始まりと終わりがある」「思考の結論は行動に結びつき、現実に変化を与える」「ゴールの設定がとても重要」への理解を深めます。
認知リテラシー入門 第3回「基本シェーマ」とは
「考える」というヒトの機能を整理したものが「基本セット」(「ゴールの設定」→「情報収集」→「判断」→「結論」)でした。今回は、ヒトの4つの機能のうちの他の二つ、「信じる」と「感じる」とが、どのように、この「基本セット」に影響を与えるかを見ていきます。「基本セット」が横軸だとすると、それを上下から「信じる」と「感じる」とが挟み込み、十字を成す、その全体を「基本シェーマ」と呼びます。引き続き、買い物をする主婦が登場します。「牛肉は国産がよい」という信念(「信じる」)によっていかに「基本セット」が効率よく回るか。月経前症候群による不安という感情(「感じる」)によっていかに「基本セット」が省エネで済むか。このように「基本セット」を使う思考のタイプを「クイック思考」と呼ぼう、と提案します。その反対に「基本セット」を丁寧に進めていく思考のタイプを「フル思考」と呼びます。別の言い方をすると、「信じる」と「感じる」の影響が強い思考のタイプが「クイック思考」。その影響が少ない思考のタイプが「フル思考」とも言えます。
認知リテラシー入門 第4回 「ぐるぐる思考」とは
まずは、第1回から第3回までの簡単な復習を踏まえて、適応的な思考(「ヘルシー思考」)とは、「クイック思考」と「フル思考」とを、必要に応じて使い分けることができる思考、と整理しています。そして今回は、いよいよ「ヘルシーではない思考」の一つ、「ぐるぐる思考」を取り上げます。典型的な二つは、過去について思い悩むパターンと、未来について思い悩むパターン。それぞれについて、「基本セット」の観点から分析します。いずれも、「ゴールの設定」が乏しく、「情報収集」と「判断」とを、まさにぐるぐる回り続けるが、「結論」を出せない、という共通の構造が見えてきます。ではなぜ、この苦しい「ぐるぐる思考」からなかなか、抜け出せないのか?それには、この「ぐるぐる思考」にメリットがあるから。何のメリットでしょうか?一言でまとめると「感情リテラシーに沿って行動を起こした結果のリスクを回避できるメリット」となります。「ぐるぐる思考」をもう一度、「基本シェーマ」の観点から分析すると、いずれのパターンも、不安や恐怖というネガティブな感情の影響が大きい。本来は、その感情の、感情リテラシーに沿って行動を起こせばよいだけ。しかし、その勇気がない。だから「ぐるぐる思考」が続く、とまとめています。
認知リテラシー入門 第5回「マイナス思考」とは
「マイナス思考」とは、認知行動療法で「べき思考」「感情の理由付け」「全か無か思考」「過度の一般化」などと呼ばれる、非適応的な思考です。それぞれの簡単な具体例を挙げますが、それだけでは、相互に無関係でバラバラな印象です。そこを、認知リテラシーの「基本シェーマ」と「クイック思考」「フル思考」の概念を活用すると、明快に整理できます。つまり、その全てが「クイック思考」になっている。本来、「クイック思考」は生存にとってメリットがあるはずですが、この場合、生存にマイナスに作用している。つまり「マイナス思考」とは、生存にマイナスに作用している「クイック思考」だ、と定義できる訳です。
認知リテラシー入門 第6回「マイナス思考」への対策その1
今回は「マイナス思考」の中の二つ、「べき思考」と「感情の理由付け」への対策を検討します。まず「べき思考」です。前回の架空の例(うつ病なのに無理に起きて弁当を作り、うつ病を悪化させる主婦)を再度、思い起こします。その「基本シェーマ」を見ると、「主婦たるものは弁当を作るべきだ」という信念(ヒトの4つの機能の一つの「信じる」)が、その主婦の「基本セット」に強い影響を与えていることがわかります。その結果、「クイック思考」になっている。それを「フル思考」に戻すことが、対策になります。まずは「ゴールの設定」。朝、起きたとき、「その時の体調によって、弁当を作るか家族に任せるか、毎回、判断する」という設定が可能です。それを踏まえて、「その朝の、自分の体調を確認する」という「情報収集」を行う。その上で、弁当を作れるかどうかを「判断」し、その結果、「弁当を作るか家族に任せる」という行動をとる。この繰り返しにより、徐々に「・・・べきだ」という信念が修正されていく。もう一つは「感情の理由付け」。前回の架空の例(自分が好きなだけなのに相手に似合うと、服売り場で青い服を強引に勧めて嫌われてしまう発達障害の女性)を再度、思い起こします。その「基本シェーマ」を見ると、「自分は青い服が好き」という感情(ヒトの4つの機能の一つの「感じる」)が、その女性の「基本セット」に強い影響を与えていることがわかります。その結果、「クイック思考」になっている。「フル思考」に戻すには、やはり「ゴールの設定」から・・・。続きは動画で。
認知リテラシー入門 第7回「マイナス思考」への対策その2
前回に続き「マイナス思考」の中の残りの二つ、「全か無か思考」と「過度の一般化」への対策を検討します。まずは「全か無か思考」。第5回で挙げた架空の例(上司に提出したレポートに一点修正があるだけで失敗だと決めつける以外、他の行動を取らない会社員)を再度、思い起こします。その「基本セット」を分析すると、「上司からの指摘がなければ合格、一点でもあれば不合格」という「ゴールの設定」が見えてきます。だから「情報収集」も、それに終始する。修正点があるかないか、それが確認できれば、ゴールが達成されるので、「このどこがダメだったのでしょうか」などの上司との会話とそれを踏まえた行動が、全く起こらない。さて、対策はどうしたらよいでしょうか?結論的には、かなりまとまった時間のカウンセリングが必要でしょう。仮に、カウンセラーがそのレポートについてプラスの材料を報告したとしても、それだけでは「全か無か思考」の修正は難しい。そもそもこの会社員は、この会社で何がしたいのだろう?その中で、このレポートにはどのような意義があるのか?この「全か無か思考」は実は、遡れば学生時代からあったかもしれない。その背景には何があるのか?その辺りの深掘りが必要でしょう。そしてもう一つの「過度の一般化」。第5回で挙げた架空の例(つらい虐待の過去を持ち、買い物にコンビニに入るも店員が男性とわかった瞬間、買い物もせずコンビニを出た30代女性)を再度、思い起こします。その「基本シェーマ」を分析すると、「男性は怖い」という信念と、「怖い」という感情とにより、「基本セット」が、トラウマの反応としての「クイック思考」になってしまう、その様子が見えてきます。対策は?続きは動画で。
認知リテラシー入門 第8回 「マイナス思考」によるカムフラージュ
今回扱うテーマは、第4回で既に少しだけ触れています。「マイナス思考」を手放すことは、なかなか難しい。その理由は「マイナス思考」にメリットがあるから、でしたね。そのメリットについて、改めて整理します。「自分が向き合いたくないものにフタをする、カムフラージュのメリット」と言えます。前回も登場した会社員(上司に提出したレポートに一点修正があるだけで失敗だと決めつける以外、他の行動を取らない)に再登場いただきます。この会社員の場合は、「全か無か思考」でした。「自分はダメだ」と決めつける、そこに何のメリットがあるのでしょうか?あり得るのは、二つ。一つは、修正が必要だった一点に向き合うことを避け、それによって「自分は優秀だ」という信念が傷つかずに済む、そのメリット。もう一つは、自分が徹底的にダメ出しを続けたら、もうこれ以上他人からダメだしをされないで済む、そのメリット、ですね。これがカムフラージュの実情です。続いて、前回も登場した30代女性(つらい虐待の過去を持ち、買い物にコンビニに入るも店員が男性とわかった瞬間、買い物もせずコンビニを出る)にも、再登場いただきます。今回はコンビニのテーマではなく、彼女とご主人との関係における「マイナス思考」を取り上げます。ご主人とトラブルがあった時、彼女はいつも「自分が悪い、自分がダメだ」という「マイナス思考」に閉じてしまう。そこには、どんなメリットがあるのでしょうか?続きは動画で。いずれの場合も、このカムフラージュにメスを入れないと、「マイナス思考」は手放せない。このタイプの「マイナス思考」は、通常の認知行動療法では対処できない、という結論になります。
認知リテラシー入門 第9回「マイナス思考」に陥りやすい精神疾患
精神疾患の中で、うつ病と躁うつ病(双極性感情障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、境界性パーソナリティ障害を取り上げます。これらの障害はいわば、脳の特性上「マイナス思考」に陥りやすい、と言えます。まず、うつ病と躁うつ病で問題となるのは、抑うつ状態という、脳の機能の低下した状態。この状態では、フル思考を丁寧にたどるだけのエネルギーがなく、やむを得ず、クイック思考になってしまいます。その結果の「マイナス思考」という訳です。抑うつ状態におけるつらい症状としての希死念慮も、フル思考を辿った末の結論ではなく、クイック思考による「省エネ」、つまり、脳の機能の低下による一つの症状、という場合が多いです。では、ADHDの場合はどうでしょう。これも「待てない」という脳の特性により、フル思考を辿ることがとても苦手。ゴールを設定し、次は情報を収集して・・・、なんてとてもやってられない。パッと「クイック思考」になって、衝動買いや、自分を責めるマイナス思考になりやすい。最後は、境界性パーソナリティ障害。この場合は「グレー(あいまい)に耐えられない」という脳の特性があります。なので、仮にフル思考を丁寧に辿っても、その結論が「グレー」なら、それに耐えられない。パートナーには良いところと悪いところがある、そんなグレーな存在、という実情に耐えられず、相手は最高、と絶賛したかと思うと、相手は最低と罵倒し尽くす。結果的に、「クイック思考」による「マイナス思考」に陥ってしまう。そして今回の結論として、これらの精神疾患が背景にある「マイナス思考」は、まずはその精神疾患に取り組んだ方がよい、というメッセージになります。
認知リテラシー入門 第10回 強迫思考
このシリーズの最終回は、強迫性障害の方に典型的な「強迫思考(強迫的思考)」を取り上げます。前回まで扱ってきた「マイナス思考」とはややおもむきが異なります。出勤前の自宅の施錠を、何回も確認し、やっと駅に向かうも、大丈夫か?と不安になり、自宅に戻り確認する、その結果、会社に遅刻する・・・、などが不適応の典型です。この「強迫思考」を「基本セット」で分析してみます。ゴールの設定は、なくはない。「確実に施錠する」です。でも、これが「自分が納得するまで確実に」となるので、どんどん、ハードルが高くなる。そして、情報収集。これは、まずは、記憶。「確かに2回、施錠した」というつい先ほどの記憶。そして「昨日もこれで大丈夫だった」などの、自分を安心させる記憶。そして、判断。「これで、大丈夫だ」。しかし・・・、ここがくせ者です。「本当に大丈夫か?」この疑問を自身に突きつけてしまい、再度、情報収集に戻る。これを繰り返す中で「確かに2回、施錠した」という、その感覚が、ふわふわと希薄になっていく。そして、確実ではない、という判断となり、結論が「自宅に戻って再度、施錠する」となってしまう。この「強迫思考」は、「クイック思考」ではない。「フル思考」ではあるが、情報収集と判断の部分が、いわばボロボロに崩れていく印象です。では、どのような対策が必要でしょうか?一定の重症度がある場合、薬物治療の併用をお勧めします。また、典型的な、強迫行為の上限を設定する行動療法も紹介します。そして、この「強迫思考」は何をカムフラージュしているのか?それは「人生でコントロールできることには限りがあるという現実」それにフタをする、そのメリットがあるとも整理しています。
もやもや解消!躁うつ病
もやもや解消!躁うつ病
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その1 人の4つの機能とは
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、「いまの主治医にはうつ病と診断されたが、セカンドオピニオンを受けたら躁うつ病と言われた」など、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。それ程、複雑な病状だとも言えます。なので患者さんにとっては、「躁うつ病」という用語は、混乱の原因になります。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その第1回目。抑うつ状態、軽躁状態、躁状態などの用語をしっかり理解するための、前提となる考え方をお伝えします。
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その2 感情と気分を区別しよう
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、「いまの主治医にはうつ病と診断されたが、セカンドオピニオンを受けたら躁うつ病と言われた」など、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。それ程、複雑な病状だとも言えます。なので患者さんにとっては、「躁うつ病」という用語は、混乱の原因になります。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その第2回目。「悲しい」などの「感情」と、抑うつ状態、軽躁状態、躁状態など「気分」との区別をしっかり学びます。
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その3 躁状態と軽躁状態
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、「いまの主治医にはうつ病と診断されたが、セカンドオピニオンを受けたら躁うつ病と言われた」など、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。それ程、複雑な病状だとも言えます。なので患者さんにとっては、「躁うつ病」という用語は、混乱の原因になります。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その第3回目。いよいよ「躁状態」「軽躁状態」について学びます。人の4つの機能という観点から、症状を整理します。また、躁状態の実際の様子もお伝えします。
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その4 軽躁状態と間違いやすい状態
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、「いまの主治医にはうつ病と診断されたが、セカンドオピニオンを受けたら躁うつ病と言われた」など、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。それ程、複雑な病状だとも言えます。なので患者さんにとっては、「躁うつ病」という用語は、混乱の原因になります。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その第4回目。軽躁状態と間違えやすい状態として、「臨床閾値下軽躁」「気分高揚者」「発達障害の過集中」を挙げ、その違いについて学びます。
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その5 双極Ⅰ型とⅡ型の違い
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その第5回目。いよいよ、双極Ⅰ型、双極Ⅱ型との違い、双極Ⅱ型と間違えやすい「臨床閾値下軽躁」「気分高揚者」「発達障害の過集中」も再度取り上げ、その違いについて学びます。
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その6 薬物治療の大原則
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その第6回目。「薬物治療の大原則」として、1:気分安定薬の内服する、2:抗うつ薬を使わない、について説明した後、気分安定薬は一生内服する必要があるのか?という疑問について回答し、その一方、日常生活の工夫も重要であることをお伝えします。
もやもや解消!躁うつ病シリーズ その7 療養の基本方針
躁うつ病は、双極性障害(双極性感情障害)とも呼ばれ、頻度の高い精神疾患ですが、精神科医によっても診断が一致しないことも多いです。その混乱を解消するために、主に診断の観点から、躁うつ病について、真っ正面から整理するシリーズ、その最終回の第7回目。「療養の基本方針」として、1:抑うつ状態になったら抑うつ状態の療養に従う、2:抑うつ状態を避けるために、躁状態/軽躁状態を起こさない、3:躁状態/軽躁状態を起こさせないために断固として生活リズムを維持する、4:躁状態/軽躁状態が自分の本来の状態だとは思わない、という4点について説明しています。
今さら聞けない発達障害
今さら聞けない発達障害
今さら聞けない発達障害 その1 自閉症スペクトラム障害
昨今、発達障害に関する情報はネット上にあふれています。でも、発達障害に特徴的ないろいろな特性が、どのような基本的な体験世界に由来するものなのか、その本質的な理解を促す情報は、乏しいと言わざるを得ません。その不足している情報を補う、このシリーズの1回目は、自閉症スペクトラム障害についてです。乳幼児期の、母子関係に焦点を当てて、その体験世界を分かりやすくお伝えします。
今さら聞けない発達障害 その2 注意欠陥多動性障害(ADHD)
昨今、発達障害に関する情報はネット上にあふれています。でも、発達障害に特徴的ないろいろな特性が、どのような基本的な体験世界に由来するものなのか、その本質的な理解を促す情報は、乏しいと言わざるを得ません。その不足している情報を補う、このシリーズの2回目は、注意欠陥多動性障害(ADHD)についてです。注意のコントロールのあり方と、ワーキングメモリーという観点から、その体験世界を分かりやすくお伝えします。
初心者のための精神科のかかり方
初心者のための精神科のかかり方
初心者のための精神科のかかり方 1 精神科の薬の注意点
初めて精神科にかかろうとする時、一昔前より敷居が低くなったとは言え、いろいろ不安に思うことが多いはずです。また、当院を受診したいが、ずいぶん先の初診までとても待てない、他の医院さんを受診した後、改めて当院を受診しよう、と考える方も多いです。そのような方のために、これだけは注意して下さい、という内容をまとめたシリーズです。今回は、問題の多い、精神科の薬(向精神薬)についての注意事項です。
初診者のための精神科のかかり方2睡眠衛生チェック8項目
睡眠衛生とは、良質の睡眠を取るために行った方がよいとされる基本事項を意味する用語です。当院は初診まで時間がかかるので、その間に、睡眠に関する困りごとであれば、ご自身で睡眠衛生を確認することで、改善される可能性があります。今回は、睡眠衛生に関する8項目をピックアップして紹介します。その8項目とは、1:起床時間と就寝時間を一定に保つ、2:無理に寝ようとしない(寝付けない場合は一旦、寝床から離れる)、3:午後以降は飲酒を控える、4:寝る前は覚醒作用のあるカフェイン(コーヒー)やニコチン(たばこ)を控える、5:室内を暗くし、適切な室温(低め)に保つ、6:週に数回は息がハアハアする程度の運動をする、7:寝る前はスマホ(によるブルーライト)を避ける、8:気になることは睡眠前に解決しておく、になります。最後に、これはしてください(Do)として、睡眠導入剤を処方されてもされなくても、睡眠衛生に沿って習慣を修正しましょう。これはしないでください(Don't)として、無理に習慣を修正するのは控えましょう(逆に不眠になる)とまとめています。
初心者のための精神科のかかり方 3 どのような症状のときに受診すべきか?その1
初心者のための精神科のかかかり方シリーズの、3回目です。どのような症状があれば、精神科のドアを叩くのがよいのか?主要な精神疾患を順場に挙げ、その典型的な症状と、見落とされがちな症状までを、網羅的に整理しました。分量が多いので、この3回目を、3つに分けて、お伝えする、その1回目です。うつ病、躁うつ病、パニック障害、社会不安障害、強迫性障害、適応障害について解説しています。
初心者のための精神科のかかり方3 どのような症状のときに受診すべきか?その2
初心者のための精神科のかかかり方シリーズの、3回目、その2、です。どのような症状があれば、精神科のドアを叩くのがよいのか?前回のその1に続き、主要な精神疾患を順場に挙げ、その典型的な症状と、見落とされがちな症状までを、網羅的に整理しました。今回は、統合失調症、妄想性障害、心的外傷後ストレス障害、摂食障害、甲状腺機能亢進症、境界性パーソナリティ障害について解説しています。
初心者のための精神科のかかり方3 どのような症状のときに受診すべきか?その3
初心者のための精神科のかかかり方シリーズの、3回目、その3で、精神疾患の説明では最後の回です。どのような症状があれば、精神科のドアを叩くのがよいのか?前回のその2に続き、主要な精神疾患を順場に挙げ、その典型的な症状と、見落とされがちな症状までを、網羅的に整理しました。今回は、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、アルコール依存症、認知症について解説しています。そして、この3回を通じての、これはしてください(Do)と、これはしないでください(Don't)もまとめています。Doは、少しでも困っていたら、こんな症状ですが見てもらえますかと、精神科に相談の電話を入れること。また、体の症状も出てくるので、内科への受診もオススメです。Don'tは、困っているのに誰にも相談せず自分で抱えてしまう。これはやめましょう、というメッセージで終わります。
初心者のための精神科のかかり方4 精神科医にできること・できないこと
精神科医なら「こころに関することならなんでもやってくれる」と思われているかもしれませんが、決してそうではありません。精神科を受診する前に、受診して落胆しないためにも、精神科医に何が出来て何ができないか、整理しておきましょう。まず、出来ることとして、・精神疾患を診断する、・それに基づいて、休職や入院などの判断を行う、・それに関連する書類を発行する、・精神疾患について患者さんに説明する、・精神疾患に対する薬物治療を提供する、・精神疾患の療養に関する簡単な生活指導を提供する、・短時間ならグチを聞く、これらを挙げています。では、何ができないのでしょうか?実は、まとまった時間、例えば30分とか50分の心理カウンセリングは提供できません。理由はいくつかありますが、一つは、そのようなカウンセリングの修練を積んでいない、ということです。精神科医の専門資格として、精神科専門医、という資格がありますが、その資格は、そのような修練を求めていません。つまり、その資格だけでは、カウンセリングの能力は保証されない、ということです。市中の多くの精神科クリニックで、まとまったカウンセリングの時間を期待して受診すると、落胆する結果になります。そこは割り切りましょう、と提案しています。
初心者のための精神科のかかり方5 心療内科との違い
精神科と区別がしにくい科として、心療内科があります。何が違うのでしょうか?心療内科は、精神疾患ではなく「心身症」を診る科だ、という整理がわかりやすいでしょう。心身症とは、体に確かに不具合があるが、その症状の変化に、精神的な要素が与える部分が大きい、そのような一群の身体疾患だ、と言えます。典型例は、気管支ぜんそく。聴診器を当てると確かに、ヒューヒューと喘鳴が聞こえます。でも、両親のケンカがひどくなるなど、家庭環境や母子関係などの影響により、症状がひどくなる。このような病状に対して、ぜんそく治療薬の処方などの内科管理を提供しつつ、家族関係への心理的サポートも行う、このような状況が、心療内科の専門医が最も輝く瞬間でしょう。しかし注意が必要なのは、心療内科の専門医でも、精神科専門医の資格がない場合、重い精神疾患の治療経験が乏しい場合がある。ところが、世の中の精神科のクリニックは、ほとんどが、心療内科と精神科を二つ、標榜している。これは、どう理解したらよいのでしょうか?ここには、業界のウラ事情が潜んでいます。率直な実情をお伝えし、要は、何の専門医資格を持っているか、しっかり見極めようとお伝えしています。ウラ事情の続きは動画で。
初心者のための精神科のかかり方6 神経内科との違い
精神科が扱う疾患と一部、重なる疾患を扱う科に、神経内科があります。精神科は、精神神経科と呼ばれる場合もあるので、一層、両者の違いが、標榜科の名称だけでは、とても判別できません。このシリーズの5回目、心療内科との違いを扱った場合と同様に、標榜科のイメージではなく、診てもらいたい疾患と、それを診ることができる専門医の資格、という観点から、その違いを整理します。
PSM
PSM
PSMとは
PSMとは、サイコソマテック・マイノリティ(psycho-somatic minority)の略で、心身の反応における少数派、という意味の、当院の造語です。いろいろな「心身の反応」について具体例を挙げながら、その基本的な意味についてお伝えします。最初は、パニック発作。閉所での息苦しさから、パニック障害の診断に至るまで、その間にはグラデーションがあることを、実演しつつ説明します。どこからを障害・疾患と呼ぶか、その線引きは、いわば社会の側の都合で、診断基準という形でなされていることも知ります。そして、うつ病や自閉症スペクトラム障害の例も交えつつ、精神疾患を、正常と異常、という区別で理解するのではなく、多数派と少数派の違いとして理解することを勧めています。そうすると、マイノリティゆえに社会から不利益を被る構造も見えてくるでしょう。
PSMというコンセプトの意義
PSMとは、サイコソマテック・マイノリティ(psycho-somatic minority)の略で、心身の反応における少数派、という意味の、当院の造語です。前回の「PMSとは」の内容を踏まえた上で、「精神障害者」という呼称ではなく、「PSM」という呼称を用いる意義について、説明します。その意義の一つは、その呼称を用いることで、正常と異常、健常者と障害者、という分割から自由になれる、という点です。それは、精神疾患によりセルフスティグマの緩和にも貢献します。もう一つは、医療という枠組みに振り回されずに済む、という点です。医療はどうしても、異常を正常へ、障害者を健常者へと矯正しようとします。それが噛み合わない場合は、多数派へ近づこうとする方向ではなく、少数派としての生活を探る方向に切り替えやすくなります。そして、「障害者」という用語は、「少数派であることによって社会から不利益を被る場合があるから、その社会からサポートを受ける権利がある者」とい意味に理解することをお勧めします。